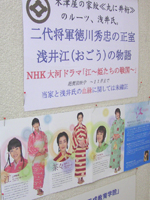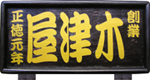浅井氏
浅井三姉妹
浅井三姉妹は、浅井氏で最も有名な人物です

浅井三姉妹こと、浅井茶々(淀殿)、初、江の3人は、戦国大名浅井長政と正室お市の方の娘でございます。お市の方は、織田信長の妹でございます
写真 : 淀殿 ( 浅井茶々 )の墓
- 佳木山太融寺 ( かぼくさん たいゆうじ )
- 高野山真言宗
- 大阪市北区太融寺町3-7
- 鴫野 淀姫神社より移祀
織田信長の姉は、木津屋のご先祖 大橋家に嫁ぎました → 大橋氏
江〜姫たちの戦国〜
浅井三姉妹を描いたNHK大河ドラマ「江 〜姫たちの戦国〜」が、放映されました
NHK総合テレビ(日曜日 夜8時)他 2011年1月9日から11月27日
NHK大河ドラマ特別展「江〜姫たちの戦国〜」(滋賀展)
平成23年7月23日(土)〜8月31日(水) 長浜市長浜城歴史博物館 (滋賀県長浜市)
浅井茶々が使用したと伝わる帯も展示されました。茶々の帯には「丸に井桁」の家紋が入っております
浅井氏の家紋
丸に井桁
浅井氏の家紋は、通説では「三つ盛亀甲に花菱」とされていますが、浅井の「井」の文字にちなんだ井桁紋も使っておりました。どちらかと言うと、戦国武将化する以前の浅井家にとって「丸に井桁」が本来の家紋だったのではとも考えられます
浅井氏の井桁紋
- 丸に井桁紋の入った浅井茶々の帯が残っております
- 養源院の浅井長政や浅井久政の位牌には丸に井桁紋が入っております
- 医光寺の浅井家と三好家の合同位牌には丸に井桁紋が入っております
- 徳勝寺蔵の浅井亮政夫妻像は、両人のお召し物に井桁の紋が入っております
- 高野山持明院蔵の浅井久政像は、脇差に井桁の紋が入っております
ある時期から「三つ盛亀甲に花菱」を定紋とし、「丸に井桁」を替え紋(裏紋)として使っていたとも考えられます
養源院
養源院は京都東山区にあるお寺でございますが、寺名は浅井長政の法名に由るもので、浅井長政、浅井久政の霊を弔うために淀殿(浅井茶々)の願いにより建てられたお寺でございます。養源院には、浅井長政、浅井久政の位牌が安置されていますが、この位牌に「三盛亀甲に剣花菱」ではなく、井桁の紋が使われております。このような鎮魂の場において使われている「井桁紋」こそが、浅井氏にとっての本来の家紋ではないでしょうか。戦国時代の短い期間に使われた、比較的新しい「三盛亀甲に剣花菱紋紋」ではなく、昔から長年守り続けてきた「井桁紋」こそが、浅井氏にとって魂の拠り所と言える家紋と想われます
養源院は創建から25年で火災に因り消失いたしましたが、崇源院(浅井お江)の願いにより再興されています
井桁紋・井筒紋

近年は家紋が整理されて、固定化されております。しかし戦国時代においては、家紋はまだまだ進化発展の流動的な時期で、丸に井桁、井桁紋、井筒紋等は、混同して使われていた事もあるかと考えられます。徳勝寺蔵の浅井亮政夫妻像は、現代の一般的な呼び方で言うと井筒の家紋に当ります
↑ 写真 : 浅井三代の菩提寺である、滋賀県徳勝寺の紋章 「井桁」
三つ盛亀甲に花菱
三つ盛亀甲に花菱紋は、浅井氏にとっては歴史の浅い家紋であったのではないでしょうか。この家紋が何処から来たのかは、今の所、私には定かではございませんが、戦国の世に大きく花を咲かせ、儚く散っていたということは間違いありません
(家紋についての考察は、木津屋治郎兵衛に拠るものです)
浅井氏の子孫
一般に、浅井氏は滅亡したとされています。それは、浅井亮政、浅井久政、浅井長政と続いた宗家のお話です
しかし、浅井亮政の兄弟等から派生した浅井氏一族には、その後も続く流れがございます
浅井明政
浅井新三郎明政(田屋明政)は、浅井亮政の娘鶴千代(海津殿)の婿養子でございます。明政は、亮政の養父直政からの本家筋にあたり、亮政の後継者として「新三郎」と「政」の字を継承しております。しかし、明政は家督を継ぎませんでした
浅井久政が後継者となった事で、浅井明政の血筋は途絶えることなく、そにお後に繋がる流れが出来ました。「一線に身を置く事の危険」、「脇役になった事により生かされた命」というものを感じます
浅井直政
浅井明政の孫浅井直政は、 浅井三姉妹の三女、お江(おごう)が、二代将軍徳川秀忠の正室となった事で、浅井姓を名乗り続ける事を憚り、外戚の三好姓に改めました
浅井氏の外戚に三好氏がございました。血縁を含め、深い繋がりが合ったと考えられます
浅井氏と三好氏
三好長慶
浅井亮政は、三好長慶と同盟を結んでおりましたので、その頃には、外戚関係にあったのではと思われます。戦国の世では、家と家が同盟を結ぶ場合、嫁の行き来で外戚関係になるのが一番手っ取り早く、また確実だったのではないでしょうか。まさに、浅井三姉妹のお江のように、武家と武家との策略に、振り回された女性も多かったと思います。また、養子縁組も然りでございます
豊臣秀勝
浅井三姉妹の江の2番目の夫である豊臣秀勝(羽柴秀勝)は、豊臣秀吉の姉日秀(にっしゅう)と三好吉房の次男で、ここでも、三好氏と浅井氏の繋がりがございます
三好三人衆
浅井氏が近江で六角氏対立していた時、三好三人衆(三好長逸、三好政康、岩成友通)は、浅井氏側に付いておりました。この時期にも、浅井氏と三好氏の外戚関係は進んでいたのではないでしょうか
三好氏について 三好氏
浅井国幹
明治時代の医師、浅井国幹(こっかん)のお家は、武家の浅井三代と始祖を同じくします。浅井国幹先生の流れは、尾州徳川家の藩医宗を七代も勤めるお家でございました
医系の浅井氏
- 参考文献:「浅井氏家譜大成」「浅井系統一覧」
- 家紋:丸に井桁
- 医祖;浅井盛政
浅井氏の出自
浅井氏は、丁野を起源とする一族でございます。現在の岡本神社辺りに屋敷があったと伝わっております。出自(しゅつじ)に関しては、幾つかの説がございます
三條
かみんぐす〜ん
物部守屋
かみんぐす〜ん

石山合戦
本願寺と織田信長が戦った石山合戦において、浅井氏は本願寺に付いて戦いました。石山合戦は11年にも及びました
木津城
本願寺勢力の中枢として、木津城の城主となって戦った当家の御先祖は、この石山合戦においても、浅井氏との繋がりがあったと考えられます
木津城/木津の砦について → 木津城
浅井氏の研究
浅井氏については、素晴らしい研究をされている先生方がいらっしゃいますので、このページでは、当家を中心にした考察に留めさせて頂きます。また、編集者の木津屋治郎兵衛は、歴史専門家ではなく、一介の商人(あきんど)であることを含み置き頂けますようお願いいたします
浅井氏の子孫
当家のように戦国武将の浅井氏の子孫の方がいらっしゃいましたら、情報のご提供をお願いいたします。浅井氏に関しましては、浅井三代や浅井三姉妹以外の情報は少なく、今後、研究されるべき課題と思います。よろしくお願いいたします