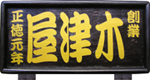上賀茂神社
上賀茂神社 ( かみがもじんじゃ )と、社家の子孫である木津屋について
下鴨神社については → 下鴨神社
賀茂別雷神社
上賀茂神社は京都市北区の神社。 正式名称は賀茂別雷神社( かもわけいかづちじんじゃ )
ご祭神は、賀茂別雷大神 ( かもわけいかづちのおおかみ )です
社家
賀茂氏
古代の日本には、大きく分けて二つの賀茂氏がありました。賀茂県主氏 ( かものあがたぬしうじ )と賀茂朝臣氏 ( かものあそんうじ )です
賀茂県主氏
上賀茂神社の社家は、賀茂県主氏によって守られてきました
上賀茂神社は、御祭神の子孫が創祀し、社家によって守られてきました。社家の初代から30数代くらいまでは木津屋のご先祖です (代数は諸説あり)
写真 : 賀茂県主氏/賀茂氏の子孫 ↑
鴨川
上賀茂神社、および下鴨神社のそばを流れる鴨川は、両社家の賀茂氏に由来し、この名前が付いています。京都の町を貫く鴨川は京都の顔であり、今も尚、賀茂氏の勢いの名残があります
賀茂玉依比売命
片山御子神社
← 賀茂玉依比売命 ( たまよりひめのみこと )を祀る片山御子神社( かたやまみこじんじゃ )
賀茂玉依比売命は、上賀茂神社の御祭神である賀茂別雷大神( かもわけいかづちのおおかみ )の母です
玉依日売とも表記されます
建玉依比古命
土師尾神社
← 建玉依比古命 ( たけたまよりひこのみこと )を祀る土師尾神社( はじおじんじゃ )
建玉依比古命は、賀茂玉依比売命の兄で、賀茂県主氏の祖です。建玉依比古命の子孫が代々、上賀茂神社を祀りする宮司、および社家となりました
鴨建玉依彦とも表記されます
若宮神
若宮神社
若宮神をお祀りしています。若宮といえば、主たるご祭神の御子神様。しかし、御祭神の賀茂別雷大神には御子神はいません。では、祖父にあたる賀茂御祖神社ご祭神の鴨建角身命の若宮は、建玉依比古命です。しかしそれならば、土師尾神社があります。という考察から、御祭神は判りかねます。秘されているのかもしれません
素直に考えると、賀茂県主氏の神であるだろうと推測されますが、訳ありの神様かもしれません
← 写真手前の渡廊の後ろ側に御鎮座。奥は本殿
一般の参拝はできません。また、お社は見れなくなっています
〜 その他、境内の紹介 〜
本殿
大きな丹塗矢(にぬりや)
丹塗矢の正体は、火雷神 ( ほのいかづちのかみ )とされています
御祭神 : 賀茂別雷大神
国宝
西側に権殿があります
新宮神社
御祭神 : たかおかみのかみ
水神様。オカミは龍の古語です
← 奉納された龍の切り絵、「龍神図」
川尾神社
末社
ご祭神 : 罔象女神 ( みつはのめのかみ/みづはのめのかみ/みずはのめのかみ )
水神様。 御物忌川 ( おものいがわ )のそばに御鎮座
弥都波能売神とも表記される
賀茂山口神社
祭神 : 御歳神 スサノオノミコトの孫
沢田川のすぐ前、渉渓園(庭園)向かって御鎮座
御物忌川と御手洗川
御物忌川(おものいがわ)と御手洗川(みたらしがわ)の川合。 左が御物忌川
この後、ならの小川となります
楢の小川
境内を流れる楢の小川/ならの小川
正式名称は御手洗川( みたらしがわ )
和歌に詠まれています
「 風そよぐ ならの小川の 夕暮れは みそぎぞ夏の しるしなりける 」 藤原家隆
藤原家隆 → 公家の墓
渉渓園
曲水庭園の渉渓園 ( しょうけいえん )
曲水宴( きょくすいのうたげ )という歌を詠む会が催される庭園です
神馬
神馬舎
希少な神馬
神馬のいる神社は、十数社ほどしかありません
神山号 ( こうやまごう )
競走馬出身です
紫式部
紫式部がお参りしています
紫式部が詠んだ歌
「 ほととぎす 声まつほどは 片岡の 森のしづくに 立ちやぬれまし 」
紫式部のページ → 紫式部
葵祭
葵祭 ( あおいまつり )は、京都三大祭りの一つです
葵祭の起源
起源は欽明天皇の時代で、この時の宮司は木津屋のご先祖です。正式名称は賀茂祭で、長らく、「賀茂祭」「賀茂の祭」と呼ばれていました
葵祭を始めたのは木津屋のご先祖でございます
葵祭の牛車(ぎっしゃ) →
フタバアオイ
祭りの色々な所に二葉葵 ( フタバアオイ )が飾り付けられることから、葵祭と呼ばれています
フタバアオイは賀茂葵(カモアオイ)とも呼ばれ、上賀茂神社に自生しています
上賀茂神社の西側に上賀茂葵之森町という町がありますが、この辺りはかつて。フタバアオイが群生していたと伝わります
↑ 木津屋のフタバアオイ
フタバアオイを育てて増やす → 葵プロジェクト ( afuhi.jp )
源氏物語
紫式部の源氏物語に、葵祭 ( 賀茂祭 )が登場します
「第九帖 葵」に葵祭の場面があります
葵祭の観覧における車の争いが、生々しい臨場感で描かれています
← 写真 : 源氏物語 (瀬戸内寂聴 著)
「三十三帖 藤裏葉 ( ふじのうらば )」では、紫の上が、祭神の御降臨のお祭り(御阿礼神事)、そして、賀茂祭(葵祭)に参ります
「第四十一帖 幻」では、葵祭 ( 賀茂祭 )の日に、源氏の院が中将の君に歌を詠んでいます
「 おほかたは 思ひ捨ててし 世なれども 葵はなほや 摘みをかすべき 」
→ 紫式部
葵祭の観覧
上賀茂神社創祀&社家の子孫と共に参る葵祭
令和八年、観覧の会、参加者を募っています (会費なし)
5月15日(金)
悠久の時や神の御縁を感じながら観覧するというおもしろみがあります
応募、おまちしています
令和七年の葵祭 → 葵祭 2025 (木津屋の旅)
二葉葵紋
神紋は、葵祭でも有名な「二葉葵」です
徳川家の「三つ葉葵紋」の元になりました
← 上賀茂神社 本殿
徳川家について → 徳川家と木津屋
ヤタガラス
上賀茂神社の御祭神 賀茂別雷大神の祖父は、鴨建角身命 ( かもたけつぬみのみこと )と云い、下鴨神社に祀られています。この鴨建角身命は、八咫烏 ( ヤタガラス )であると伝わっています。八咫烏は神武天皇が東征の折に導いたと伝わります
写真 : 阿倍王子神社御烏社 八咫烏大神の御烏尊像 2022年
賀茂大社
賀茂社
創建から長らく、賀茂社と称していました。上賀茂神社と下鴨神社がひとつで賀茂社です。今も、二つの神社を総称して賀茂神社と呼ばれています
写真 : 「賀茂大社」の碑
下鴨神社
下鴨神社こと、賀茂御祖神社(かもみおやじんじゃ)は、上賀茂神社御祭神の母と、その父を祀っています
御祭神 : 玉依姫命 ( たまよりひめのみこと )、賀茂建角身命 ( かもたけつぬみのみこと )
この賀茂建角身命の子孫が、上賀茂神社と下鴨神社を創祀し、社家となり守ってきました
下鴨神社( 賀茂御祖神社 )は、上賀茂神社の創祀の後にできたと伝わっています
→ 下鴨神社
賀茂神社
上賀茂神社・下鴨神社と同じ御祭神を祀る神社が各地にあります
○ 寝屋川市の加茂神社 → 寝屋川 加茂神社 (木津屋の旅)
○ 大阪市の蒲田神社
社家町
上賀茂神社の南側に社家町があります
かつては社家の一族が住み、今も屋敷が残されています
室町時代に今のような形になったとされ、木津屋のご先祖もここに住まいしました
斎院
社家とは別に、賀茂神社に奉仕する斎院 ( さいいん )という役職がありました。賀茂斎王、賀茂斎院とも云います
初代から35代の斎院の内33人は、木津屋のご先祖がかかわっています
斎王代
斎院は、戦後の葵祭の斎王代 ( さいおうだい )につながっています
子孫・末裔
木津屋は、上賀茂神社創祀者、および社家の子孫です。また、下鴨神社の社家と共通の先祖を持っています
子孫の定義は、血を受け継いでいるということです。末裔(まつえい)という言葉もあります。活動の規模を客観的に見て、末裔という表現が的確かもしれませんが、末裔という言葉には勢力が衰えているという感があり、好ましく感じないので、子孫と表現させて頂いています
社家
木津屋のご先祖には、社家(しゃけ)がいくつかございます。社家は、神社の神職を代々世襲して務める家です
上賀茂神社の他には、下鴨神社(祭神)、八坂神社(祇園)、津島神社、熱田神宮、籠神社、石清水八幡宮、鹿島神宮、大宰府天満宮、宗像大社、伊勢神宮の社家の血を継承しています
その中でも上賀茂神社は、宮司をつとめた代数が30数代ほどと長く、木津屋とは縁が深い神社です
【 四方拝 】
上記の内、伊勢神宮、熱田神宮、上賀茂神社、下鴨神社、石清水八幡宮、鹿島神宮は、宮中で元旦におこなわれる四方拝(しほうはい)の対象になっている神社です
賀茂別雷神社(上賀茂神社) : 京都府京都市北区上賀茂本山339
上賀茂神社社家の子孫 木津屋 大阪府大阪市西区南堀江4-23-27 06-4391-0704