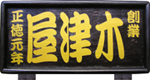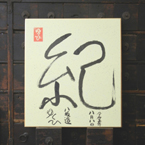八坂神社
【 八坂の会 】 TOP 予定と記録 祇園祭 文献 祇園信仰 出雲系
〜 京都祇園 八坂神社の始まりから、子孫 日下家までの歴史 〜
八坂神社の創祀・創建
伊利之
京都祇園 八坂神社の由来は、当家のご先祖が創祀(創建)したとされています
スサノオノミコトを祀り始めたと伝わる伊利之( いりし )です
八坂神社の歴史 ( 八坂神社のサイト )
【 日本書紀の記述 】 巻第二十六 斉明天皇紀
二年秋八月癸巳朔庚子、高麗遣達沙等進調。大使達沙・副使伊利之、總八十一人。
【 新撰姓氏録の記述 】 山城国諸藩
八坂造 : 出自狛国人之留川麻乃意利佐也 (意利佐 = 伊利之)
【 八坂神社の社伝 】 斉明天皇二年(656)、高麗の調度副使、伊利之使主(いりしおみ)の来朝
八坂の里
伊利之の子孫は、八坂の里(八坂郷)に住まいしました。八坂の里は、八坂神社の南側の地域で、八坂の搭の法観寺、高台寺のあたりと推測されます。八坂は、「也佐加」や「也佐賀」とも表記されました
創祀と創建
創祀は、神様を祀り始めるということで、創建はお社を建立することと考えます。伊利之が創祀した時には、今の八坂神社ような立派なお社は建立されていないと考えます
八坂造
八坂造 ( やさかみやつこ )
当家のご先祖は、八坂造の姓(かばね)を賜り、長き代に渡り祇園社(八坂神社)の長、執行(しぎょう)でありました
八坂神社の境内であった円山公園 ↑
社家
社家 ( しゃけ )
祇園社(八坂神社)は、社家と呼ばれる家(当家のご先祖)が守っていました。社家は明治時代になるまで受け継がれ、少なくとも鎌倉時代までは代々世襲されていました
祇園社の社家は、後に、宝寿院と呼ばれるようになりました
祇園祭
祇園祭 ( ぎおんまつり )
平安時代、祇園社(八坂神社)の社家である八坂造により始められました
当家ご先祖の八坂造が、祇園祭を作った人です
京都 祇園祭(ぎおんまつり)は、日本の三大祭の一つとされています
祇園祭の歴史、観覧 → 祇園祭
祇園社
京都 八坂神社は、祇園感神院( かんじんいん )、祇園社、祇園神社と呼ばれていました
八坂神社の名は、明治時代からのものです
紀氏
紀氏 ( きうじ )
鎌倉時代に紀氏の血が入り、皇別紀氏を称するようになりました
祇園社(八坂神社)は、紀氏が祭祀して参りました
↑ 紀氏が祭祀をおこなう日前神宮・國懸神宮
津島神社
堀田氏
堀田氏 ( ほったし/ほったうじ )
祇園社20代目のころに、ご先祖は尾張(愛知県)の津島神社に移り、祭祀をおこなうようになりました
祇園から移った堀田俊重は、尾張津島天王の初代の祠官となり、堀田家代々の子孫に受け継がれていきました
弥五郎殿社 : 堀田弥五郎正泰 ( ほった やごろう まさやす )の造営
堀田家の始祖である武内宿禰公と大巳貴命を祀る
↑ 堀田家住宅 (重要文化財)
武家 堀田家
津島神社社家の堀田氏から武家になる流れがあり、小早川家、織田家、豊臣家、徳川家に仕えます。ご先祖の中から紀州徳川家に仕える流れが出ました。紀州徳川家からは将軍が輩出され繁栄しました
発起人家と徳川家 → 徳川家
小野氏
小野氏 ( おのうじ )
その後、堀田氏のご先祖が小野氏に婿養子に入り、八坂造の血が小野氏、そして日下家へと受け継がれました
日下家
日下家 ( くさかけ )
小野氏から分かれた家で、聖徳太子から賜った姓「日下」を継承
小野氏と日下家 → 日下
【 八坂神社 社伝 】
京都 八坂神社の起源は、二つ語られています
【 血統 】
ご先祖や子孫というのは血筋のことであり、すべてが宗家ということではありません
(八坂造が20代で津島神社へ など)
八坂の会
八坂の会 ( やさかのかい ) それは、いやさかな会です
八坂神社、スサノオのミコトと親しむ会です。ごいっしょに楽しんで頂ける人を募っています
会費はございません。お電話、メールでお知らせ下さい
弥栄
弥栄(いやさか)な活動をしていきたく想います
● スサノオノミコト、牛頭天王を祀る神社の参拝
● 京都 祇園祭との関わり (観覧など)
● スサノオノミコト、八坂神社の研究
● 大国主神、熊野大社など、つながりの神々、神社の参拝
祇園祭 奉賛
八坂の会のある木津屋では、京都 祇園祭の期間(一週間前より)、祇園祭の盛り上げの催しを行なっています
八坂造の子孫
世襲により30代、800年に渡り、スサノオノミコト(牛頭天王)を祀った社家の子孫による運営
発起人 : 八坂造の子孫、日下治郎兵衛( くさかじろべい ) 〜 創祀者から43代目
スサノオノミコト
掛けまくも畏きことですが、系図の上では、スサノオノミコトの子孫であります
建速須佐之男命 〜 饒速日命 〜 武内宿禰 〜 紀氏 〜 八坂造 〜 発起人
他に、 建速須佐之男命 〜 大国主命 〜 和珥氏 〜 小野氏 〜 発起人
かしこみかしこみ、もまおす
八坂とのご縁
発足前からの、八坂神社、スサノオノミコトとのご縁
彌榮神社 (生野区桃谷)
八坂神社上の宮 (大正区三軒家東)
天保4年9月1日 京都祇園神社より勧請
明治41年7月 難波嶋町 八坂神社(慶安4年御鎮座)を合祀
杭全神社 (平野区平野宮町)
八阪神社 (東成区中道)
海老江八坂神社 (福島区海老江)
伊和志津神社 (兵庫県宝塚市伊孑志)
茅の輪くぐり
2015.7.7
敷津松之宮 (浪速区)
旧社名 : 松本宮、牛頭天王社、八坂神社、木津祇園宮
← 摂社 : 日出大国社(大国主神社) 2015.3.5
難波八阪神社
綱引神事の八岐大蛇 ( やまたのおろち )
← 2013.2.24
日下久悦 →
( 本殿の前 )
日下久悦氏 : 牧野富太郎博士の支援者であり、天王寺舞楽を守った人物
( 牧野富太郎博士については、NHK連続テレビ小説「らんまん」を )
大川神社
2011.5.15
止止呂支比賣命神社
2009.11.25
子孫・末裔
木津屋は、八坂神社創祀者、および社家の子孫です
子孫の定義は、血を受け継いでいるということです。末裔(まつえい)という言葉もあります。活動の規模を客観的に見て、末裔という表現が的確かもしれませんが、末裔という言葉には勢力が衰えているという感があり、好ましく感じないので、子孫と表現させて頂いています
社家
木津屋のご先祖には、社家(しゃけ)がいくつかございます。社家は、神社の神職を代々世襲して務める家です
八坂神社、津島神社の他には、熱田神宮、上賀茂神社、下鴨神社(祭神)、石清水八幡宮、鹿島神宮、籠神社、大宰府天満宮、宗像大社、伊勢神宮の社家の血を継承しています
その中でも津島神社は、社家から分かれてからの年数が浅く、木津屋とご縁の深い神社です
社家は、熱田神宮の大宮司家のような宮司の長の家と、権宮司の家などもあり、大きな神社ほど多くの社家があったようです
八雲立つ 出雲八重垣 妻籠みに 八重垣作る その八重垣を すさのおのみこと
八坂神社 : 京都府京都市東山区祇園町北側625
【 八坂の会 】 大阪府大阪市西区南堀江4-23-27 木津屋 06-4391-0704